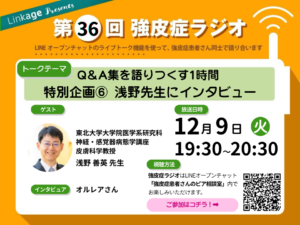先日の「強皮症ラジオ 〜週末だョ!息抜きしナイト〜 5/24 編 」配信に向け、リスナーのみなさまから事前にお寄せいただいた、オススメ”レシピ”をご紹介いたします!
レシピだけではなく、調理法やオススメアイテムなどのご紹介もありました。ぜひ、お試しください。お便りをお届けいただきました皆様、ありがとうございました!
「キャベツのポタージュ」

材 料
・キャベツ
・玉ねぎ
・にんじん
・じゃがいも
・豆乳または牛乳
・コンソメまたは鶏がらスープ
・塩胡椒、オリーブオイル
※それぞれの分量はご自身の食事量にあわせた適量をご用意ください。
作り方
①全ての野菜を適当なサイズにカットして少量のオリーブオイルで炒める
②コンソメスープで柔らかくなるまで10分くらい煮る
③豆乳、または牛乳をコンソメスープの半量くらい注ぎ、塩胡椒
④ブレンダーでポタージュ状にして出来上がり
コメント
まとめて作って冷凍保存もオススメです。食事の際、最初に飲むと胃をコーティングしてくれるようで胃炎になりづらくなりました。
「発酵しょうが」

材 料
・生姜
用意するもの
・おろし金、ボール、キッチンペーパー
・保存容器(小瓶など)
作り方
①手を清潔に洗う。保存容器を消毒しておく。
②生姜は皮をつけたままよく洗い、水分をしっかりと拭き取る。
③おろし金で皮ごとすりおろす。
④おろした生姜を清潔な瓶に入れて冷蔵庫で2週間くらい保存して待機。
ポイント
余分な水分が混ざると腐敗の原因になるため、生姜を洗ったらしっかりと水気を拭き取りましょう。また、保存容器に詰める際は、隙間や空気が入らないように保存容器に詰めます。
★おろし金を使わず、フードプロセッサーを使ってもOKです!
コメント
本当に便利で、料理のたびにパッと使えるので重宝しています。生姜湯もすぐに作れます。材料は生姜だけなので、チューブの生姜のように添加物も気になりません。
「セイロで作る蒸し料理」

材 料
・お好みのお野菜
・お肉(鶏ササミなど)
用意するもの
・蒸し器、蒸篭など
作り方
とにかく、野菜を切って蒸篭で蒸すだけで、野菜は、甘くなるし、お肉のササミはフワフワに!
コメント
1日に1度は、必ず蒸篭のメニューにしていたら、その効果なのかは定かではないですが、血液検査のコレステロールの数値が正常値になりました!
「ボーンブロス(骨スープ)」

材 料
・手羽元 など骨つき肉
・生姜やネギなど
作り方
①新鮮な手羽元を洗ってお肉に2.3ヶ所切れ目をいれる
②お水を入れてグツグツと50〜60分炊く
★生姜やネギを一緒に入れると風味が良くなります
ポイント
澄んだ綺麗な鶏がらスープができるので、濾してから和洋中と好きなように味付けをして、具を足します。参鶏湯風にもできます。
時短の場合は、圧力鍋で調理も可(5〜10分加圧して放置)。
たくさんできたら、小分けにして冷凍も可。
コメント
腸にはとても良いようです。骨は牛豚鶏と何でも良いのですが、なかなか手に入りにくいので、私は簡単に手に入る”手羽元”を使います。
以前オフェブの副作用で下痢が酷かった時に、毎日このスープを飲みました。同時に小麦粉や甘いものも控えると、下痢をする日はほとんど無くなりました。
インスタントの鶏がらスープに比べて、このスープはかなり美味しいので勧めです。
「スパイスクッキー」

材 料
・米粉…50g
・片栗粉…20g(全粒粉)
・ハチミツ…35g
(デーツシロップ)
・ココナッツオイル…35g
纏まらなかったら豆乳で調整。
☆ここからはお好みの分量で
・干しぶどう
・紅茶葉(桜)…1p
・シナモン…2ふり
・カルダモン…2ふり
・クローブ…1ふり
・ジンジャー…1ふり
☆お好みで
・生ローズマリー(適量)
・黒胡麻を入れても美味しいと思います。
作り方
一般的なクッキーの作り方・オーブンの機能を使ったクッキーの焼き方に合わせる。
ポイント
材料を見れば、殆どがホールでの記載でハードルが高い様に感じますが、粉末でも十分美味しく仕上がりましたのでご安心下さいね。
コメント
スパイスには温め効果で冷えや便秘を解消したり、香りの満足感で食べすぎを防いだり、また、スパイスの種類によって様々な健康効果が期待できるため、日常的に摂取することで体の不調を整える効果が期待できるらしく…。クラフトコーラにハマってから、スパイスを紅茶やケーキ、パン等に入れて作っています。
クッキーが作れない方は、”クラフトコーラ”は煮るだけなので作り易いと思います。材料、作り方等はYouTubeやGoogle検索で!
「味噌汁に入れる豆腐の切り方」

食材のカット方法
味噌汁に入れる豆腐の切り方。
包丁を上手に使えなくなり、サイコロ形に切れなくなりました。そこで、大きいスプーンを使って三日月状にすくって入れています。片手に豆腐を乗せるなんて無理無理、レイノー症状も出てきますよね。今は形にこだわらず、この方法にして楽しています。
コメント
*麻婆豆腐には”冷凍豆腐”が扱いやすく、オススメです!市販の袋では開閉がしにくいので、スライダータイプの冷凍袋に入れ替えて使ってます。
「飯を炊く時の味変」

材 料
・お米
・お煎餅
作り方
①炊飯器でお米をセット
②適量のおかき、煎餅をバキバキして(大きくても OK)入れて炊きます。おこわにも似てます。
ポイント
これで、タコ味、小魚味、イカ味などになります。
たくさん入ったお魚パックを買わなくても、食べたいものに最後は辿り着けます。笑。
コメント
レシピの紹介とは別で…電気圧力鍋買いました。圧力でどんな硬い肉もホロホロに、キャベツもドッサリ入れます。白菜も血行に良いので冬場はたくさんトロトロにして食べます。
「母レシピの玉ねぎスープ」

材 料
・玉ねぎ … 1個をみじん切り
・にんじん(小)半分
・しめじ(半分)一株
・わかめ 一つかみ(乾燥)
・昆布(顆粒) 出汁(8g)
・いりこ(顆粒) 出汁(8g)
・しじみ(即席味噌汁の溶かすタイプ)
・あさり(即席味噌汁の溶かすタイプ)
作り方
鍋で30分以上コトコト煮る。(うわずみを取る)
コメント
脳動脈瘤と狭心症をした母が10年以上飲んでるスープです。作って鍋ごと冷蔵庫に入れて欲しくない時もそれだけは飲んでいるそうです。検査も先生に褒められたと喜んでました!私は、毎日は作れなくてとりあえず、”粉のオニオンスープ”を飲むようにしてます!
「父レシピの長芋とろろ」

材 料
・長芋(山芋)
・お酢
・お醤油
・生卵
・味付けのり
作り方
長芋をすって、酢としょう油と生卵を混ぜて味付け海苔をとろろの上にバラバラと入れて出来上がり!
ポイント
海苔は、大きな手でグッシャっと潰す感じ!
コメント
ツルツル入っていくので美味しかったし、よかったです!
体調いい時は、自分で長芋を買って帰り、父を待ち、ただいまという父に『おかえりなさい』と長芋を差し出す娘でした!(笑)
今は、”冷凍のやまいも”を買って生卵と味ポンを入れて食べてます。(*^^*)
「ツタンカーメンえんどう豆」

オススメ食材
ご近所さんから珍しいえんどう豆(豆の色は緑いろ)をいただいたエジプトからやって来た「ツタンカーメンえんどう豆」のご紹介!
作り方
炊飯器で豆ご飯炊きました。しばらく放置して炊飯器の蓋を開けると なんと!白米がピンク色になっていました!
コメント
エジプト王ツタンカーメンの墓から発掘された豆が日本に渡って来たそうです。なんともロマンチックで不思議な豆ご飯を頂いて”元気モリモリ長生き”しそうです♪ 来年は育ててみようと思います。
「鶏ひき肉のあんかけ豆腐」

材 料
・絹ごし豆腐 … 1丁
・鶏ひき肉 … 100g
・めんつゆ … 大1
・出汁(かつおちゃん) … ひとつまみ
・水 … (カップに1カップと1/2カップ)
・吉野葛粉末 … 小1
・水 … 大1
作り方
①豆腐を8等分にする
②水をカップ1+1/2にめんつゆと出汁を入れておく
③吉野葛粉末小さじ1を水大1で溶かしておく
④鍋にひき肉を入れて炒めます
⑤豆腐をレンジ600ワットで1分30秒温めます
⑥炒めたひき肉にカップに計っためんつゆと水溶きの吉野葛粉末を入れ、木べらでゆっくりかき混ぜます。2分程でトロミが付いて来ます。
⑦温めた豆腐にあんかけをかけていただきます。
ポイント
片栗粉はが30秒程でトロミが付いて来ますが、身体が芯から温まるのは吉野葛粉なので愛用してます!
コメント
葛を使った身体に優しいご飯です。逆流性食道炎の頃、今は少し治まってますが良く食べてました。ひとくち20回噛むような食べ方をしていました。
分量は色々作ってみましたが、この分量が良かったです。
手に強張りがあると作りにくいかも知れません。ある時、右手が突然強張りましたのでグーで木べらを握ったら少し力が入りました。
「黒糖生姜煎じ茶」

材 料
・水 … 1ℓ
・黒糖 … 大さじ2〜3(20〜30g)
・生姜 … 1かけ(厚さ2ミリにスライス)
作り方
材料をお鍋に入れて、沸騰させ15〜20分コトコト煎じたら、出来上がりです。
出来上がり量は約600mlに減ってます。
ポイント
黒糖はお砂糖よりもカロリーがちょっと低いのと、ミネラルが豊富なのが特徴です。
コメント
これは私が去年胆汁まで吐いちゃった時に、知り合いの中国人の鍼灸師さんに教えてもらいました。
不思議とスッキリ飲めて、それ以来1年近く毎朝作って薬を飲む時に飲んで、1日で飲み切ってます。
飽きっぽい私が一年近く続いてるのは、体に合ってるからなのかなぁと思っています。
是非一度、作って飲んでみてくださいね。
いかがでしたでしょうか。
どれも、手軽にやってみよう!と思えそうなやさしいレシピばかりでしたね。
それぞれ作り手さんのやさしさが伝わるレシピには、ちゃんと理由やエピソードがあるんだなあと感じました。みなさまの食卓でも「ちょっと試してみようかな」と思っていただけるきっかけになればうれしいです。
作ってくださった方の心にも、食べた方の体にも、じんわり届いていたらうれしいです。
また、みなさまの「やさしい味」や「身体の不調を整えられそうなレシピ」、「手先がおもうように動かなくてもこんな調理法があるよ!」など、ぜひお寄せいただけると、またラジオやホームページからもお届けできればと思います。
みなさまからの“やさしい手料理”、また”おかわり”をお待ちしております^^